組織崩壊マニュアルからアンチパターンで学ぶ、強い組織の作り方
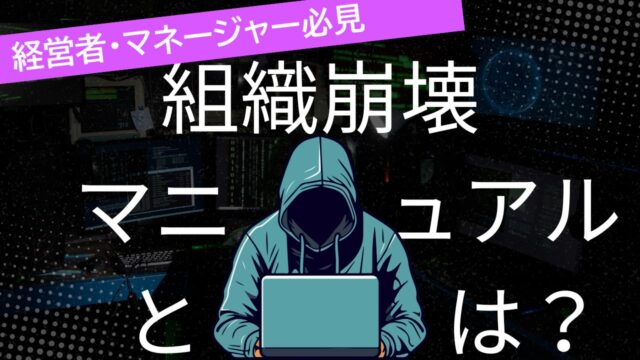
突然ですが、あなたの職場でこのような言葉が飛び交っていませんか?
- 仕事の依頼は正式な文書でしか受け付けません!
- あ、文書に誤字があったので依頼は請けられません。
- 言い回しが適切でないので依頼は請けられません。
その状況、組織が弱体化を始めている兆候かもしれません…
実はこれらの行動、かつてスパイを養成するために作られた「サボタージュマニュアル」に記された、組織を弱体化させるための戦略の一部なのです。
本記事では、そんな驚くべきマニュアルの内容を紐解き、現代のホワイトカラー業務における「あるある」なサボタージュの実態を組織づくりのアンチパターンとしてご紹介したいと思います。
会社を経営する立場の方、事務・管理部門で組織運営に携わる方は、ぜひこの記事を通して、自社の現状を客観的に見つめ直すキッカケにしてみてください。
- 組織づくりのアンチパターンとして、サボタージュマニュアルの概要を理解できる
組織を停滞させ崩壊へ導く7つの行動とは
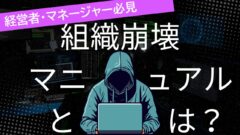 サボタージュマニュアルは元々がスパイを養成するマニュアルだったということもあり、サボタージュ活動といいつつ過激なことが書かれています。(妨害活動やら破壊活動など)
サボタージュマニュアルは元々がスパイを養成するマニュアルだったということもあり、サボタージュ活動といいつつ過激なことが書かれています。(妨害活動やら破壊活動など)
あえて私から言うまでもないですが、内容としては普通に犯罪行為なので参考にするのはやめましょう。
一方で、ホワイトカラー業務(事務職・管理職)におけるサボタージュ活動は、令和の時代を生きる私たちから見るとちょっと笑ってしまうくらい「あるある」な話に溢れています。
ざっくりまとめると次の7つです。
- 形式的な手順を過度に重視せよ
- ともかく文書で伝達せよ
- 会議を開け
- 行動するな、徹底的に議論せよ
- コミュニケーションを阻害せよ
- 組織内に衝突・を作り出せ
- 士気をくじけ
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」とはよく言ったもので、成功にパターンはないが失敗には共通パターンがあることをイメージできると思います。
形式的な手順を過度に重視せよ
 まず最初のサボタージュ戦略は「形式的な手順を過度に重視する」というものです。これは私たちがイメージする「お役所仕事」に近いかと思います。
まず最初のサボタージュ戦略は「形式的な手順を過度に重視する」というものです。これは私たちがイメージする「お役所仕事」に近いかと思います。
そもそも数名程度の小さな組織では、担当者同士のコミュニケーションや相互サポートによって仕事の目的が達成されるのが一般的です。
しかし、人員が増えて仕事が複雑化するにつれて、担当者間の相互協力だけでは対応しきれなくなります。
そこで「形式的な手順」を整備する必要が出てくるわけです。
形式的な手順を整備することは「業務品質の維持」や「企業統治(ガバナンス)」の面で重要であり、組織が成長する上で健全な流れと言えるでしょう。
しかし注意すべきは、細かいことに気づくのが得意な人(あるいは、細かいことしか目に入らない人)が、体裁や手順の正しさのみを指摘するようになってはいないか?です。
本来なら重要視すべきはずの仕事の中身が軽視され、「仕事の目的を達成すること」よりも「体裁や手順が正しいかどうか」が重視されるようになってしまう状況こそ、組織が硬直し始める前兆となります。
ともかく文書で伝達せよ
 常識で考えると、お互いの共通認識を見える化し、効率化を進める手段として「仕事の指示をテキストや文書で統一」という営みは効果があるかのように思えます。
常識で考えると、お互いの共通認識を見える化し、効率化を進める手段として「仕事の指示をテキストや文書で統一」という営みは効果があるかのように思えます。
しかし、サボタージュマニュアルでは全ての指示・伝達を文書で行うことこそ組織の硬直に繋がると指摘しています。
具体期には「正式な文章でないと受理しない」「細かい言い回しや形式の誤りに対して際限なく注文や文句をつける」という仕事の進め方です。
というのもそもそも口頭で指示を行っていれば、受け手とのコミュニケーションを通して「AよりもBの方が効率的だ」とか「この方法ならCさんを巻き込んで進めよう」などの生産的な議論が生まれ、より効率的に仕事を進められます。
指示する側が考えきれなかったような領域・視点について、受け手側がより深い知見を持っていれば、よりよい仕事の進め方など議論できる可能性もありますね。
それが文書での指示を過剰なまでに徹底することで、指示の誤りを訂正することすら難しくなりますから、組織のスピード感が失われ組織が硬直していってしまう、という理屈です。
会議をひらけ
 「会議を開催する」というのはコミュニケーションの頻度を増やし、関係者間の意思統一を図るうえで優れた考えかのように思えますが、何が問題なのでしょうか?
「会議を開催する」というのはコミュニケーションの頻度を増やし、関係者間の意思統一を図るうえで優れた考えかのように思えますが、何が問題なのでしょうか?
本の中ではいくつかの問題点(社会的な手抜き、評価を気にして意見を控える、多数派の意見に迎合してしまう、発言を待っているだけのぼーっとしている時間が多い、など)が挙げられています。
個人的な感覚ですが、似たような話で「過去に大きな成果をあげた人」の意見を否定しづらい、というのも会議開催の問題点のひとつとして考えられるケースだと思います。
例を挙げますと…
現場に出ている若い方の感覚がより市場の実態を掴んでいたとしても、過去の成功体験に囚われている時代遅れの上司の意見が通りやすい、というのはどの会社でもある話ではないでしょうか。
「20年前に数十億の案件で会社を大きく成長させたが、現場から離れて10年経つ部長」と「毎週10人の経営者と会って議論を交わしている3年目の若手」の発言では、やはり前者の方が重要視されますよね。
仮に事実として後者の方が正しく、これからの市場環境を捉えていたとしても。
行動するな、徹底的に議論せよ
そもそもの話。客観的なデータを集めて、定量的に分析し、考えられるリスクを検討してから意思決定する…こういったプロセスは従業員の生活を背負う経営者からすれば至極当然のことですよね。
しかしここでのポイントは延々と時間やお金をかけ、情報収集や考えられるリスクについて議論し続ける、というのが問題で、より良い意思決定とは情報収集を良いタイミングで打ち切り、施策の実行に移ることだ。ということのようです。
筆者はこの話を聞いて、ソフトバンクの孫さんの言葉を思い出しました。孫さんは
5割の確率でやるのは愚か。9割の成功率が見込めるようなものはもう手遅れだ。7割の成功率が予見できれば投資すべき
という基準で投資判断を行うようですが、これはまさに不確実性の高い新規事業へ参入などについても同じようなことが言えるのかも知れません。
コミュニケーションを阻害せよ
 素晴らしい仕事をする上で、関係者間のコミュニケーションが重要であることは言うまでもありません。
素晴らしい仕事をする上で、関係者間のコミュニケーションが重要であることは言うまでもありません。
実際、著しく高い成果を挙げたチームの共通点を解明した「プロジェクトアリストテレス」によると、心理的安全性の高い職場こそ、優秀な人材を確保よりも重要だという調査結果が出ました。
つまり、
- 直接話ができる
- 親しみやすい
- 自分も間違うことを積極的に開示する
- 失敗を学習の機会だと公言する
- 具体的な指示を出す
と言う文化が成果を上げるチームには必要だ、と言うことです。
つまりサボタージュの観点に立つなら、上司・リーダーであるあなたは部下や同僚にこう言えば良い訳です。
「また失注か?早く成果を上げてこい!俺ならこの規模の案件をポシャらせたことないぞ!話がある?知らん。話したいことがあるならあと一件でも受注を取ってからだ!」
組織内に衝突・争いをつくりだせ
 マネージャーの役割として、チームの成果を最大化する「パフォーマンスマネジメント」と、メンバー間の良好な関係性と信頼を築く「メンテナンスマネジメント」の2つがあるとされています。
マネージャーの役割として、チームの成果を最大化する「パフォーマンスマネジメント」と、メンバー間の良好な関係性と信頼を築く「メンテナンスマネジメント」の2つがあるとされています。
後者のメンテナンスマネジメントを軽んじてしまうと、組織内に様々な問題が生じ、深刻な事態を招くとのこと。
某動画配信サイトを運営する企業では、ブリリアント・ジャーク(仕事はできるけれど人間性に問題があり、周囲に悪影響を与える人物)を採用しない、というルールがあるようですが、これもメンテナンスに悪い影響を与える可能性を排除する施策なのかもしれませんね。
また組織の外ではなく、内部に敵を作りだしてしまうのも問題とされています。
外部のライバル企業との競争はむしろ健全で、社内での派閥争いや過度な出世競争などでメンバー間の不和や対立を生み出し、敵を内部に作り出してしまうよう状況こそが問題(=サボタージュとして有効)だ、ということです。
「外の敵は組織を団結させるが、内側の敵は組織の力を大きく損なう」というのは国家の統治レベルでも言える普遍的な話とされていますので、マネージャーや経営者は注意しておく必要がありますね。
士気をくじけ
 サボタージュマニュアルで士気をくじく方法として挙げられているのが、いわゆる「学習性無力感」です。
サボタージュマニュアルで士気をくじく方法として挙げられているのが、いわゆる「学習性無力感」です。
どんなに頑張っても評価されない、評価・報酬に返ってこない、という状況が続くと人間は無力感を感じてやる気が損なわれるという構図ですね。
具体的には「非効率的な作業員に心地よくし、不相応な昇進をさせよ。効率的な作業員を冷遇し、その仕事に対して不条理な文句をつけろ」とされています
…なんと極悪な!笑
やる気のある若者からやる気を削ぐための方法は、100年近く前にはすでにマニュアル化されていたようです。
逆転の発想で、組織強化を考えるキッカケに。
突然ですが…あなたは碑文谷 潤 教授をご存知でしょうか?
20年ほど前に「人の怒らせ方」を紹介していく番組があったのですが、碑文谷教授(番組の中だけに存在する方です。俳優さんが演じられています)の
【参考】碑文谷教授のミッドナイトゼミナール 今さら人に聞けない!怒らせ方講座 -Wikipedia
そうです。サボタージュマニュアルを読むことで「うちの会社で起きてることやんけ!笑」というエンタメ的な楽しみ方だけでなく、サボタージュマニュアルのような仕事の進め方を避けることで組織強化に活かせる、という考え方です。
今回の内容をアンチパターンとして、より良い組織づくりの参考にしてみてください。
大阪・京都の関西圏のお客さまを中心にDXコンサルティングを提供するnonet 株式会社では、今回ご紹介したサボタージュマニュアルのような営みを否定し、「テクノロジーで、”らしさ”を取り戻す。」のビジョンを掲げています。
考える組織、強い組織づくりに興味があり、力を発揮したいという想いをお持ちの方はぜひこちらからご応募ください。

Seeds4biz〜”ビジネスのタネ”がみつかるメディア〜では、
小さな会社に役立つ「デジタル化・DX化」「業務改善」「マーケティング」といったテーマを中心に幅広い情報を発信しています。起業準備中・新規事業やりたい系の人も見てね。

