「成果を出すマネージャー」を目指すあなたに教えたい”業務仕組み化”のヒミツ
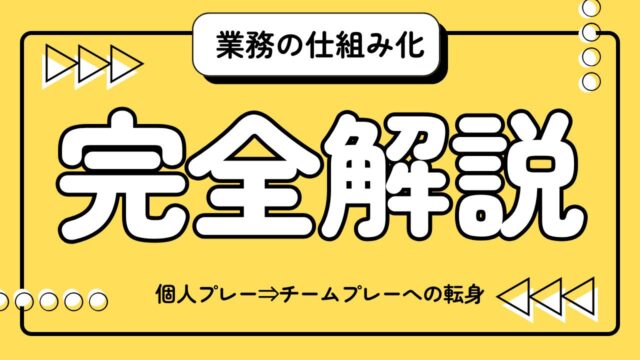
「チームのマネージャーとして、部署の成果を最大化する方法に悩んでいる…」
今日は「業務の仕組み化」を切り口に、その解決策について考えていきたいと思います。
具体的には、チームメンバー個々人の頑張りに依存したマネジメントから脱却して、 “仕組みで勝つ”ための業務仕組み化を実現する5ステップについてです。
チームで成果を上げられるマネージャーになるヒントにしてみてください
似たような悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
【無料ダウンロード】Google Workspace活用ガイド
- メリットA
約4万年前までヨーロッパを支配していたとされるネアンデルタール人です。
現代に住む私たちからすると「知能の高いサピエンスがネアンデルタールに勝ったんでしょ?」と考えがち(実際、私もそう思っていました)ですが、実はネアンデルタール人、我々よりも頑強な肉体を持っており、脳の容量も大きかったそうです。
具体的に言うとマンモスのような大型動物を仕留める能力も持っていたとか….つまり個々の戦闘能力や環境への適応力においては、私たちサピエンスを上回っていたようなんですね。
 しかしネアンデルタール人は、フィジカルや知能に劣る我々サピエンスに敗れ、地球から姿を消しています。一体なぜなのでしょうか?
しかしネアンデルタール人は、フィジカルや知能に劣る我々サピエンスに敗れ、地球から姿を消しています。一体なぜなのでしょうか?
一説によると、身体的に非力なホモ・サピエンスは「共通の物語(ビジョン)」を信じる力で、大規模で柔軟な群れを組織し、知恵と情報を共有して生き残った、というものがあるそうです。
飛躍しすぎかも知れませんが、私には「共通の目的とビジョンを掲げることがいかに重要であるか」という教訓に感じられました。
業務の仕組み化を実現するための5ステップ
ステップ1:目的の明確化|なぜやる?やるとどうなる?
 業務の仕組み化に着手する前に重要なのが、目的・ビジョンの明確化です。
業務の仕組み化に着手する前に重要なのが、目的・ビジョンの明確化です。
「私たちは、仕組み化によって何を実現したいのか?」「どんな未来が欲しくて、業務を仕組み化するのか」です。
例えば、それは…
- 残業を減らし創造的な仕事をするため?(生産性向上)
- ミスを減らし、顧客からの信頼を高めるため?(業務品質UP)
- 品質を下げずにコストを下げるため?(コスト削減)
この「なぜ」という目的を最初に共有することで、「仕組み化」は面倒な作業ではなく、全員で未来へ向かうためのワクワクするプロジェクトに変わります。
この目的こそが、プロジェクトが行き詰まった時に立ち返るべき指標、あらゆる意思決定のコンパスになります。
ステップ2:現状把握 |全ての業務を洗い出す「業務棚卸し」
 まず、チームの業務を「すべて」書き出します。これが「業務棚卸し」です。
まず、チームの業務を「すべて」書き出します。これが「業務棚卸し」です。
毎日作成する日報から、月に一度の請求書処理、お客様への電話対応まで。誰が、何に、どれくらいの時間をかけているのか。「業務の地図」を作成するイメージです。
「そんな時間はない」と感じるかもしれません。しかし、航海図も持たずに航路の改善ができないのと同じで、ここが最も重要な出発点になります。まずは付箋やExcelを使い、チームで「見える化」するプロセスそのものを楽しんでみてください。
■【関連記事】DX化の第一歩は遠回りに見えても「業務の棚卸し」から始めるのがオススメ
ステップ3:業務分析 |ボトルネックと非効率を発見する
業務の地図が完成したら、次はその一つひとつを吟味し、改善のメスを入れていきます。チームで地図を眺めながら、3つの視点で問いかけてみましょう。
- 「これは、本当に必要か?(捨てる)」:慣習だけで続く会議や、誰も見ていない報告書はありませんか?
- 「これは、他の人でもできないか?(分ける)」:その仕事は、本当に特定の人でなければ遂行不可能な業務でしょうか?
- 「これは、もっと楽にできないか?(変える)」:毎回ゼロから作っている資料や、何度も手戻りが発生するプロセスはありませんか?
この分析こそ管理職の腕の見せ所ですが、同時に、日常業務に深く関わる当事者だけでは、慣習という名の“当たり前”に気づきにくいのも事実です。
「その報告書、本当に必要?」「その承認プロセス、無駄が多くない?」といった視点で、業務を客観的に評価する。
このプロセスは、当事者だけでは客観的な判断が難しく、業務改善のフレームワーク第三者の視点を取り入れるることが成功のカギになります。
■【関連記事】ECRSの原則とは|改善のアイディアを磨き上げるガイドライン
ステップ4:カタ化|業務をテンプレート化しよう
 そして次に、改善策をチームの資産として定着させるために「業務のカタ化」に取り組んでいきましょう。
そして次に、改善策をチームの資産として定着させるために「業務のカタ化」に取り組んでいきましょう。
ただし、完璧なマニュアルを目指す必要は全くありません。むしろ、一枚のチェックリスト、メールの返信テンプレート、簡単なFAQといった「小さなカタ」から始めることが成功の秘訣です。
この「小さなカタ」が一つあるだけで、「あの人でなければ分からない」という属人化は劇的に解消され、あなた自身も細かな確認作業から解放されます。そして、この手動の『カタ』こそが、次のステップである『自動化』の設計図になるのです。
完璧を目指さず、まずはチェックリストやテンプレートから作成。「これさえ見れば誰でもできる」状態が仕組み化のゴール。
「誰でも出来る」の次のステップは、システムやAIに任せられないか?になる。
(ポイント)ここまでのステップは、あなた一人でも始められる重要な業務改善だが、同時に客観的な視点を持つのが難しい部分でもある、と示唆する。
ステップ5:デジタル化 |生成AIやSaaSなどのITツールを活用
「小さなカタ」で業務の土台が固まったら、次に見据えるのは、仕組みを「人が回す」から「仕組みが“自動で回る”」**状態への進化です。
ここで、SaaS(クラウドサービス)や生成AIが、私たちの強力なサポーターになります。
例えば、Excelでバラバラに管理していた顧客情報をSaaS(CRM)で一元管理すれば、情報共有は自動化され、抜け漏れはなくなります。面倒な議事録作成や報告書の要約を生成AIに任せれば、メンバーはより創造的な業務に時間を使えるようになります。
これらは、私たちが汗をかいて作った「設計図(カタ)」を、デジタルの力でミスなく、24時間365日動かし続けてくれるパートナーです。テクノロジーを賢く使うことで、チームは日々の雑務から解放され、本当の意味での「未来を創る仕事」に集中できるのです。
特に最近では生成AIやAIエージェントの構築、SaaS同士のAPI連携を組み合わせ、より高度な自動化・DX化を実現する未来も見えてきます。
“仕組み”で勝つ。そのためには
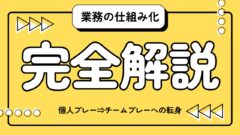 この記事で考える優れた管理職・マネージャーとは、プレイヤーとして最前線で火消しに奔走するスーパーマンではなく、チームが将来にわたって勝ち続けるための「仕組み」を設計し、改善し続けることが出来るような人物像です。
この記事で考える優れた管理職・マネージャーとは、プレイヤーとして最前線で火消しに奔走するスーパーマンではなく、チームが将来にわたって勝ち続けるための「仕組み」を設計し、改善し続けることが出来るような人物像です。
「業務改善」や「DX」は、もはや情報システム部門だけの仕事ではありません。
日々の業務の課題や可能性を最も深く理解しているのは、他の誰でもない、現場に立つあなたです。あなたが「変える」という旗を振ることで、チームは初めて未来へ向かって動き出すのです。
とはいえ、日々の業務に追われる中で、何から手をつけるべきか、誰に相談すればいいのか、頭の中が整理できないのも無理はありません。
その場合は、業務の棚卸しや生成AI/SaaSに知見をもつ外部専門家の手を借りるのもひとつの方法です。
大阪・京都の関西圏のお客さまを中心にDXコンサルティングを提供するnonet 株式会社では、生成AIにまつわる
- そもそも生成AIってどんなことができるの?
- うちの会社ならどの部署・業務で使えるの?
- セキュリティや情報漏洩のリスクは?
といったお悩み解消をワンストップでご支援する、生成AI活用コンサルティングサービスをご提供しています。
さらに毎月3社限定で「無料オンライン壁打ち会」を開催しており、壁打ちベースでご相談いただける枠を設けております。生成AI活用を検討前だという方も、せっかくのこの機会をぜひご活用ください。

Seeds4biz〜”ビジネスのタネ”がみつかるメディア〜では、
小さな会社に役立つ「デジタル化・DX化」「業務改善」「マーケティング」といったテーマを中心に幅広い情報を発信しています。起業準備中・新規事業やりたい系の人も見てね。
